国際相続とは何か?日本と海外で異なる相続制度や税務リスク、日本帰国時の注意点まで解説

人生の中でも大きな節目となる相続については、被相続人や相続人が海外に住んでいたり外国籍を持っていたりすると、「国際相続」という複雑な問題が発生します。特に海外在住の日本人や、帰国を予定している方にとっては、相続税の課税範囲や国ごとの相続制度の違い、海外資産の取り扱いなど、疑問や不安が尽きません。
「日本の相続税はおかしいのでは?」と感じる方も少なくないでしょう。本記事では、国際相続の基本から、日本と海外で異なる制度や税制、帰国時の注意点までをわかりやすく解説します。複雑な手続きをスムーズに進める参考になれば幸いです。

国際相続とは、相続人や被相続人のいずれかが外国籍だったり、海外に居住している場合に発生する相続のことを指します。日本国内だけの相続とは異なり、法制度や税制、手続きが国をまたいで関わるため、より複雑な対応が求められます。ここでは、国際相続の定義や、日本の法律・税制上でどのように扱われるのかを説明します。
国際相続の定義
国際相続とは、相続人または被相続人の一方、もしくは双方が外国籍だったり海外に居住している場合に発生する相続を指します。例えば、日本に住んでいた親が亡くなり、相続人が海外在住であるケースや、外国籍の被相続人が日本に資産を持っていたケースなどです。
このような状況では、財産が複数の国にまたがることが多く、それぞれの国の法制度や税制が関係してきます。その結果、財産の分け方や申告方法に違いが生じ、相続人同士の話し合いや慎重な判断が求められます。
制度の違いを理解しないまま手続きを進めると、税務上のトラブルや不要な負担につながる可能性があるため、正確な知識と準備が不可欠です。
日本の民法、税制上の扱い
日本の民法では、相続に関する準拠法として「被相続人の本国法」が適用されることになっています。つまり、被相続人が日本国籍であれば、居住地が海外であっても日本の法律に基づいて相続関係が判断されます。ただし、財産が外国にある場合には、現地の法律に従った手続きが求められることもあるため、注意が必要です。
一方で、相続税に関しては「居住地」や「財産の所在地」が課税の判断に影響します。被相続人または相続人が日本に10年以内に住んでいた場合、国外財産を含めて課税対象になるケースがあります。
また、日本国内にある財産については、相続人が非居住者であっても課税される可能性があるため、課税対象になるか事前に確認しておきましょう。民法と税制で適用基準が異なるため、それぞれの制度を理解した上で対応することが大切です。
日本と海外で異なる相続制度の違い

相続制度は国によって大きく異なり、分割方法や遺言の効力、相続人の範囲にも差があります。国際相続ではこれらの制度の違いが、手続きや相続内容に直接影響を及ぼすことがあります。ここでは、日本の基本的な制度と、各国の代表的な相続制度の特徴、そして制度の違いによって生じるトラブル例について詳しく見ていきましょう。
日本の相続制度の基本
日本の相続制度では、法定相続人というものが民法で定められています。法定相続人は配偶者のほか、子ども、直系尊属(両親など)、兄弟姉妹が含まれ、順位に応じて相続権が認められます。たとえば、配偶者と子が相続人となる場合、それぞれ2分の1ずつの相続が原則です。
一方、被相続人が遺言書を残している場合には、その内容が法定相続よりも優先されます。遺言によって相続分や受取人を自由に指定できますが、配偶者や子どもなどには「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されており、完全に無視することはできません。
遺言がない場合や相続人同士で意見が分かれる場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて遺産分割が行われることもあります。法律に基づいた制度でありながら、個別事情に応じた対応も重要です。
各国の相続制度の一例
各国の相続制度は日本と異なり、その国の歴史や法体系によって大きく異なります。相続人の範囲や遺言の効力、財産分配のルールもさまざまで、海外に資産や家族が関わる場合には注意が必要です。ここでは、米国・フランス・シンガポールを例に取り、それぞれの特徴的な制度を見ていきましょう。
米国
アメリカの相続制度は連邦法ではなく各州の法律に基づいて運用されており、州ごとにルールが異なります。特に相続手続きに関わる「プロベート(遺言検認)制度」は全州に存在しますが、その運用や複雑さには差があります。プロベートとは、遺言の有効性や相続人の確認、財産の分配を裁判所が監督する制度です。
カリフォルニア州やニューヨーク州などではプロベート手続きが煩雑で、回避するために「リビングトラスト(生前信託)」が広く活用されています。また、州によっては「コミュニティ・プロパティ(共有財産)」制度を採用しており、夫婦の共有財産の扱いも異なるため、相続時にトラブルが起こることもあります。アメリカでの相続には、州法の確認と事前の対策が欠かせません。
欧州(例:フランス)
フランスをはじめとする多くの欧州諸国では、「強制相続分」の制度が厳格に定められており、法定相続人に対して一定の財産を必ず残さなければならない仕組みがあります。たとえ遺言によって他の人に全財産を譲ろうとしても、子どもや配偶者といった直系相続人には法律で保障された取り分が優先され、完全に排除することはできません。このため、被相続人の意思を反映した自由な財産配分が制限されるケースが多く、日本よりも相続の自由度が低い点が特徴です。
東南アジア(例:シンガポール)
シンガポールでは、相続における「遺言書文化」が根付いており、生前に遺言を作成しておくことが一般的です。遺言によって財産の分配先を柔軟に指定できるため、被相続人の意向が反映されやすい環境といえます。
また、シンガポールでは2008年に相続税(Estate Duty)が廃止されており、相続財産に対して課税されることはありません。これにより、相続人は税負担を気にすることなく遺産を受け取ることが可能です。
シンガポールは相続の自由度が高く、税制上も有利なため、国際相続の観点から魅力的な地域といえるでしょう。
\海外口座の解約や、お金のお困りごとなら/
制度の違いによる実務トラブル
国によって相続制度が異なることから、実際の相続手続きの中でトラブルが発生することがあります。たとえば、日本では遺言がなくても法定相続分に基づいて分割されますが、他国では遺言が必須であったり、強制相続分が厳格に定められている場合があります。その結果、各国の法制度が衝突し、相続財産の分配がスムーズに進まないことも珍しくありません。
また、遺産の一部が海外にある場合には、現地の法律に従って別途手続きを行う必要があり、書類の翻訳・認証や現地専門家との連携も大切です。こうした実務上の違いを理解せずに手続きを進めると、予想外のコストや時間がかかる可能性があるため、国際相続では各国制度の事前確認が不可欠です。
海外在住者や外国籍家族が直面する相続税リスク

海外在住の日本人や、外国籍の家族が関わる相続では、居住地や国籍により日本の相続税が課されるかどうかが大きく変わってきます。課税対象の範囲や条件を正しく理解しておかないと、思わぬ税負担やトラブルに発展することもあります。ここでは、海外在住者や外国籍の家族が直面しやすい相続税のリスクについて説明します。
海外在住でも日本の相続税がかかるケースとは?
日本では、海外在住者であっても条件によっては相続税の課税対象となります。相続税法上の「非居住者」とは、日本国内に住所を有していない人を指しますが、形式的に住民票を抜いていたとしても、実質的な生活拠点や経済的基盤が日本にある場合には「住所あり」と判断されることがあるため、実態に基づいた居住状況の判断が必要です。
さらに重要なのが「過去10年ルール」です。相続人または被相続人のいずれかが、相続開始前の10年以内に日本に住所を有していた場合には、国外にある財産であっても日本の相続税の対象に含まれることがあります。
たとえば、相続人が海外転居後8年目で相続が発生した場合、日本国外の資産にも課税される可能性があります。海外に居住しているからといって安心せず、自身の居住履歴や財産の所在に応じた確認が大切です。
被相続人が外国籍の場合の注意点
被相続人が外国籍の場合でも、日本国内に財産があると相続税の課税対象となる可能性があります。日本の相続税法では、国籍よりも「財産の所在地」や「居住歴」が重視されるのが特徴です。たとえば、長年日本に住んでいた外国籍の被相続人が、国内に不動産や預貯金を保有していた場合、保有資産は課税対象となることがあるため、十分な確認が必要です。
また、相続人が日本に住所を持つ場合、国外財産を含めて課税範囲が拡大するというケースがあります。国籍だけで判断せず、資産の場所や家族の居住状況も含めて慎重に確認を進めることが重要です。
日本の相続税が他国と比べて大きく異なる部分とは?
日本の相続税制度は、他国と比べて課税範囲が広く、税率も高い点が特徴です。最高税率は55%と先進国の中でも特に高く、基礎控除額も限られているため、比較的少額の遺産でも課税対象になるケースがあります。
一方、海外では相続税がない国や、親族間の相続でほとんど課税されない国も多く存在しています。また、日本では相続人や被相続人が一定期間日本に住んでいた場合、国外に保有している財産にも課税される可能性があるため、国際相続では特に注意が必要です。
海外資産や海外送金に関する注意点
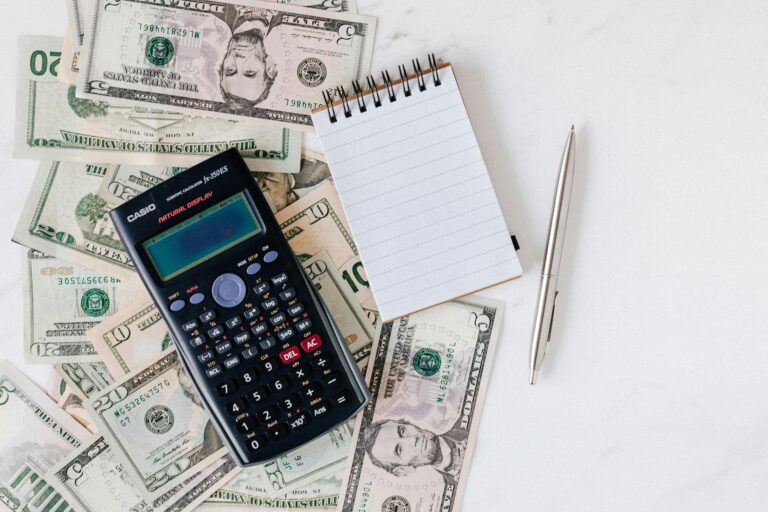
国際相続では、海外にある資産の取り扱いや相続財産の送金手続きにも注意が必要です。日本の相続税は国外に保有する資産にも課税される場合があり、送金には法律上の制限や手続きが伴うこともあります。ここでは、海外資産の課税対象や送金時の注意点について解説します。
海外資産は日本の相続税の対象になる?
海外資産が日本の相続税の対象になるかは、相続人や被相続人の居住地によって異なります。相続人・被相続人のいずれかが、相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合、国外にある資産も課税対象です。
たとえば、海外の不動産や証券、現地銀行口座の預金なども日本の相続税の対象に含まれる可能性があります。一方、双方が10年以上日本を離れている場合には、国内資産のみが課税対象となるのが一般的です。
相続財産の海外送金に必要な手続き
相続財産を海外に送金する際には、相続税の申告が完了していない場合、送金が制限される場合があります。特に高額な送金は、金融機関や税務当局によって審査の対象となり、戸籍謄本や遺言書、相続関係説明図などの提出が求められるケースも少なくありません。
また、送金には為替リスクが伴うほか、外為法による規制もあるため、申告内容と送金目的が適切であることを明確にしておきましょう。事前に必要書類を整え、送金先や金額に応じた手続きを把握しておくことが重要です。
\海外口座の解約や、お金のお困りごとなら/
日本帰国時に注意したいポイントと手続き

相続のために日本へ帰国する場合、一時的な滞在でも手続きに支障が出ないよう、事前に準備しておくことが大切です。限られた滞在期間の中で、相続登記や税務申告などを進めるには段取りが重要です。ここでは、帰国時に注意すべき手続きや必要書類について解説します。
一時帰国でも相続手続きは可能か?
一時帰国でも相続手続きは可能です。しかし、限られた期間内で戸籍の取得や相続登記、税務申告などをすべて完了させるのは簡単ではありません。各手続きには書類の取り寄せや役所・法務局への申請が必要となり、想定以上に時間がかかることもあります。
時間的に厳しい場合は、事前に委任状を作成し、信頼できる司法書士や税理士に手続きを依頼することで、帰国後の対応をスムーズに進められるでしょう。
弊社では、欧州や米国など日本から遠方に居住する相続人でも、日本国内の不動産に関する手続きや、その他相続に関する手続きを日本に帰国することなく、専門家にすべて丸投げできるサービスもご紹介可能です。お問い合わせください。
日本国内での相続税申告と納税の手続き
日本国内での相続税申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限内に、相続財産の評価や申告書の提出、納税までを完了させなければなりません。
納税は原則として現金一括ですが、資金の準備が難しい場合には「延納」や「物納」といった制度を利用することも可能です。延納は分割払い、物納は不動産などを納税に充てる方法ですが、いずれも一定の要件と申請手続きが必要となるため、早めの対応が重要です。
相続対策として準備すべき書類・事前対応
国際相続をトラブルなく進めるためには、事前の書類準備が重要です。特に遺言書や財産目録、過去の贈与記録は、相続財産の全体像を把握するうえで欠かせません。
また、海外で所有する資産の納税証明書や残高証明書などが求められることもあります。これらの書類は日本の税務署に提出する際、英語や現地語からの翻訳が必要になる場合もあるため、時間に余裕をもって準備しておきましょう。
国際相続する上で活用できる制度・対策

国際相続では、課税を最小限に抑えるための制度や事前対策を上手に活用することが重要です。特に二重課税を防ぐ「外国税額控除」や、生前の財産整理による相続税対策は効果的です。以下では、活用できる制度や具体的な対策方法について解説します。
外国税額控除制度の活用
外国税額控除制度は、国際相続において二重課税を防ぐための仕組みです。相続財産が外国にある場合、その国で相続税や類似の税が課されることがありますが、日本でも同じ財産に対して課税されると、納税者に大きな負担が生じます。
外国税額控除制度を利用することで、外国で支払った税額を一定限度まで日本の相続税から差し引くことが可能です。控除を受けるには、外国での納税証明書の提出が必要であり、申告時に日本と課税国の税制の調整を行うことが求められます。
相続税を減らすための生前対策
相続税の負担を軽減するには、生前の対策が非常に重要です。たとえば、被相続人または相続人が海外移住を検討している場合、相続発生の10年以上前に日本を離れておくことで、国外財産が日本の課税対象から外れる可能性があります。
また、財産の名義変更や生前贈与を行う際も、適切なタイミングで実施することで課税額を抑えることができます。ただし、対策には専門的な知識が必要なため、相続に詳しい税理士やファイナンシャル・プランナーに早めに相談し、100%ではなくとも全体感を把握することが効果的です。
国際相続の基本を理解し、日本帰国時などを活用して正しく相続対策をしよう!

国際相続は、日本と海外の法制度や税制の違いによって非常に複雑になるケースが多くあります。特に海外在住者や帰国を控えた方にとっては、相続税の課税範囲や財産の取扱い、送金手続きなど多くの課題があります。そのため、相続が発生する前に制度を正しく理解し、生前から準備を進めておくことが重要です。
また、日本に一時帰国するタイミングを活用して、必要な書類の整理や専門家との面談を行うことで、相続手続きは格段にスムーズになります。
OSSJでは、特に香港やHSBCに関する金融手続きのサポートに強みを持ち、各国の税制や法的手続きに精通した専門家ネットワークを通じて、安心できる対応を提供しています。国際相続に関してお困りの際は、ぜひOSSJまでお気軽にご相談ください。










