仮想通貨にかかる税金はバレないのか?実践可能な節税対策と合わせて解説

仮想通貨の売却や含み益によって利益を得た場合、仮想通貨を保有している期間は税金はかかりません。そのため、誰にも知られないようこっそり利益を得れば、納税しなくてもバレる心配がないのではと考える人がいるかもしれません。しかし、税金を支払わずにいるといずれ国税庁や税務署に知られる可能性が高く、故意に無申告であることが判明すれば追加徴税を求められるでしょう。
本記事では、仮想通貨にかかる税金を支払わなくても果たしてバレないのか、解説します。税金の無申告がバレてしまう可能性と実践できる節税対策も紹介するので、仮想通貨で利益を増やすことを検討している方、実際に利益が出ている方はぜひ参考にしてください。

仮想通貨を売却したり、取得時よりも時価が高い際に得られる含み益を得たりするときは、税金が発生します。誰にも知られずに利益を得れば、税金を払わずに済むのか、ここで解説します。
税金の無申告はバレる可能性が高い
仮想通貨にかかる税金の無申告はバレないと噂で聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、仮想通貨にかかる税金の無申告は国税庁や税務署の調査によってバレる可能性が非常に高いです。
無申告で利益をそのまま手に入れた、という人がいるという噂を聞くことがあるかもしれませんが、現実には国税庁や税務署の調査によって無申告がわかり、追徴課税を求められるケースが大半を占めています。多くの利益を得たとしても、ペナルティを加えた納税額によってマイナスになる恐れもあるため、必ず申告するようにしましょう。
仮想通貨の無申告がどのようにバレてしまうのか、その理由を紹介していきます。
仮想通貨の税金に抜け道がない理由
仮想通貨にかかる税金に抜け道がない理由は以下の通りです。
- 国税庁や税務署には所得を調査する権限がある
- 電子商取引専門調査チームがくわしい調査を実施している
- ブロックチェーンを確認して脱税を防いでいる
- 外国と租税条約を結んでいる
国税庁にある電子商取引専門調査チームでは、暗号資産を含むインターネットでの商取引に関する調査を行っています。チームの調査によって課税対象となる利益が確認されれば、所得を調査する権限を持つ国税庁や税務署が動くため、無申告であることがバレるでしょう。
仮想通貨を持つ本人が利益を得ていないと言い張る、または隠ぺいしたとしても、ブロックチェーンから嘘がバレてしまいます。仮想通貨の取引は改ざんが難しいブロックチェーンという技術を使って記録されているので、隠ぺいは不可能だと考えておきましょう。
海外の取引所を使って利益を得たとしても、外国との租税条約によって脱税を阻止されます。これらの理由から、仮想通貨にかかる税金に抜け道を見つけることは難しいといえます。
仮想通貨の利益にかかる税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円から | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、本業での所得額が300万円、仮想通貨で得た所得額が50万円だった場合の年間総所得額は350万円です。この場合は20%の税率と42万7,500円の控除が適用されるので、350万円×20%-42万7,500円=27万2,500円が所得税となります。
所得税が発生することを知らなかった、または故意に申告しなかった場合は、無申告加算税・重加算税・延滞税などのペナルティが課されます。通常の納税額に加えて、ペナルティ分も納めなければならないので、申告期限までに納めるようにしましょう。
\海外口座の解約や、お金のお困りごとなら/
仮想通貨を利用する際に実践できる税金対策
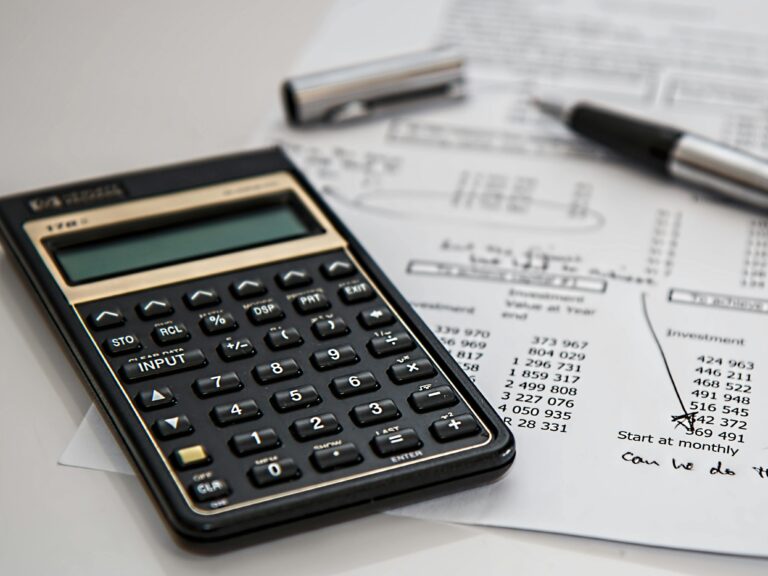
仮想通貨を利用して利益を得る際は、税金対策を実践することがおすすめです。対策をしておけば納税額を抑えられるため、税金による負担を軽くできるでしょう。ここで税金対策を紹介するので、いずれかの方法を実践してみてください。
1.長期間保有し続ける
仮想通貨で利益が出たからといってすぐに確定せず、タイミングを見定めることが重要です。保有期間は含み益に課税されないため、確定しなければ納税の必要はありません。確定したタイミングで所得税が発生すると考えておきましょう。
たとえば、本業で得るボーナスが多い年に利益を確定すると、所得額が高額になります。日本では累進課税制度が採用されているため、所得額が高くなるほど納める税額も多くなることを覚えておかなければなりません。
ボーナスが多い年は利益の確定を見送り、翌年に持ち越すなどの工夫によって納税額を抑えられます。
2.ふるさと納税や住宅ローン控除などを活用する
納税額をすこしでも抑えるために、控除を活用するとよいでしょう。個人の場合、いくつかの所得控除や税額控除などを利用できます。控除を利用すれば納税額が安くなるので、使えるものを探しておくことがおすすめです。
地方自治体への寄付金額を控除できるふるさと納税、住宅ローンを組んでいる人が利用できる住宅ローン控除などがあります。適用条件を満たしていれば利用できるため、活用できる控除があるかを調べておきましょう。
3.可能な場合は個人事業主になる
会社に勤めていない、またはフリーランスで仕事をしている方は個人事業主になることがおすすめです。一定の所得を得ている個人事業主は、毎年確定申告をしなければなりません。確定申告の際、10・55・65万円のいずれかの控除を使えるため、納税額を抑えられます。
青色申告であれば55・65万円のどちらかの控除を適用できますが、開業届や青色申告の申請書を提出する必要があります。また、日々の帳簿や収支の内訳などを記載した書類も確定申告時に提出しなければならないので、自身の状況にあわせて白色か青色を選択しましょう。
4.年間の利益確定額を20万円以内に抑える
年間の利益確定額を20万円以内に抑えれば、納税の必要はありません。仮想通貨は売却することで利益を得られます。仮想通貨購入時よりも価値が高くなったタイミングで売却すれば、含み益を得ることが可能です。
ただし、納税を回避するために無理に利益を20万円以内に抑えようとすると、大きな利益を得る機会を逃してしまう可能性があります。そのため、例えば所得税の最低課税ラインである195万円以下で利益を確定させるなど、多少の税金が発生しても問題ない程度の利益を確保しつつ、売却のタイミングを慎重に見極めることが重要です。
5.複数の仮想通貨の損益・損失で利益を相殺する
複数の仮想通貨を所持している場合は、損益・損失で利益を相殺することも可能です。たとえば、仮想通貨Aで+60万円、Bで-40万円の損失が出ているとしましょう。この場合、プラスとマイナスを相殺して仮想通貨で得る全体の利益を20万円にできます。
6.iDeCoや個人年金などの所得控除を利用する
老後の資金を積み立てつつ、所得控除にも活用できる方法を実践することもおすすめです。iDeCoは老後資金を積み立てながら、積み立てた金額を所得控除として活用できます。個人年金も同様に所得控除が使えるため、利用可能なものを選ぶといいでしょう。
節税対策を実践して仮想通貨にかかる税金を抑えよう
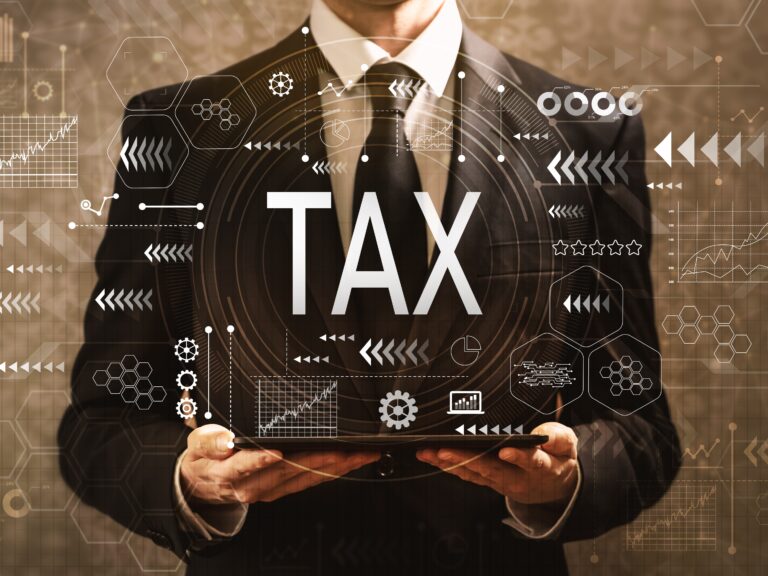
仮想通貨の利益にかかる税金から逃れることは非常に難しいため、節税対策を実践することがおすすめです。対策をすることで納税額を抑えられるので、得られる利益を多くできるでしょう。ここで紹介した節税対策を参考に、実践できるものを探してみてください。
また、最近の話題として、仮想通貨を保有したまま万が一亡くなってしまうと、適切な資金管理や相続対策をしていない場合、遺族に大きな負担をかけてしまう可能性があります。最悪の場合、資産にアクセスできず、家族から恨まれるといった思いもよらないリスクを背負うことになりかねません。そうした事態を避けるためにも、しっかりと対策を講じることが重要です。必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
また日本からの移住を考えていたり、海外での仮想通貨を含めた資産運用を検討している方は、OSSJにご相談ください。
OSSJは、複雑な海外の金融手続きに関して、特に香港やHSBCに関するサポートを得意としています。各国の税制や法的な手続きについても、信頼できる専門家とのネットワークを活用し、安心して進められるようお手伝いします。何かお困りの際は、まずOSSJまでご相談ください。
\海外口座の解約や、お金のお困りごとなら/










